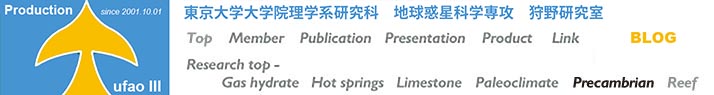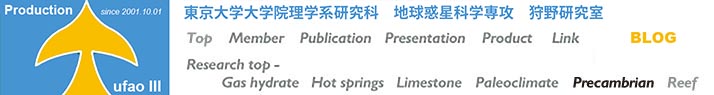近年,先カンブリア紀の研究の進展は目覚ましい。それは,ジルコンU/Pb年代法の進歩により,地層に残されたイベントの国際的な対比と時系列が解明されてきたからであろう。1990年代以降示された成果の中で特に重要なものは,28-21億年前の酸素革命に関するもの,8-6億年前の全球凍結に関するものの2つである。
初期大気の酸素濃度については長い間の論争があったが,イオウ同位体の非質量依存分別で決着がつきそうである。これは,少なくとも24億年前までの大気中の酸素濃度が現在の数万分の1であることを示すと同時に,メタンが主要な温室効果ガスとして働いていたことを示唆する。この考えは,現在の約8割程度しかなかった太陽エネルギーの下でも,地球が凍結しなかったという事実とも整合的である。ただし一方で,28億年前の地層から酸素発生型光合成を行うシアノバクテリア起源のバイオマーカーも発見されており,その後,数億年間にわたり地球が嫌気的だった理由については議論が残されている。
|
| もう1つの重要な仮説である「全球凍結」は広い氷礫岩(右図)の分布とその直後の極端に低い炭素同位体値により提唱された。少なくとも,Sturtian (~720 Ma) とMarinoan (~635 Ma) の2回の氷河期は汎世界的に認められており,「全球凍結」の真偽はさておき,重大な氷河活動が起ったことは広く受け入れられている。また,Marinoan直後の地層からの動物胚化石の発見も大きなトピックである。これは,現時点で最古の動物の証拠であり,同時期のイオウ同位体や鉄成分の検討結果は大気海洋系での酸素分圧の上昇を示唆している.そこで,全球凍結直後の酸素濃度の増加が多細胞生物の進化を可能にしたと解釈されている。しかし,なぜ酸素濃度が急増したかについては明らかにされていない。 |
 |
| 本研究室では,1999年から中国での調査を開始し,主にMarinoan氷期から原生代末 (542 Ma) に堆積した地層について研究を進めてきた。特に,炭素同位体層序から導き出される海洋構造の変遷や,リン酸塩堆積物に含まれる動物胚化石の産状(下図)と保存過程の検討,有機物の成分組成から考察される生態系をテーマとして扱っている。 |
|
|