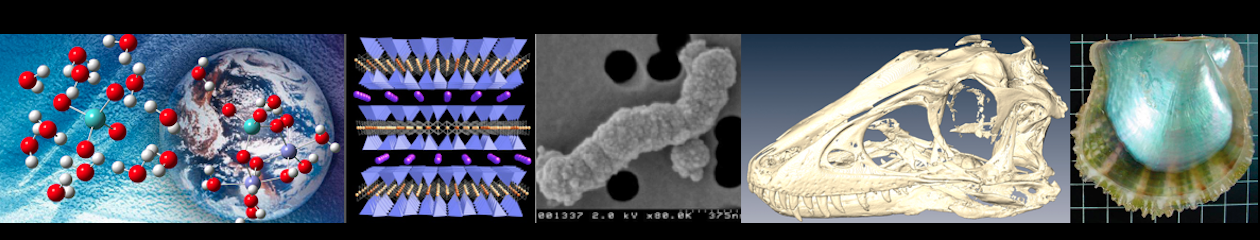日時:2025年4月7(月) 17:30~18:30(発表45分,質疑15分)
講演者:Buz Barstow (Associate Professor, Biological and Environmental Engineering Atkinson Center for Sustainability Senior Faculty Fellow, and Carl Sagan Institute Fellow, Cornell University)
演題:The Microbe-Mineral Atlas and Biomining for Metals for the Sustainable Energy Infrastructure
要旨:
Climate change is one of the biggest challenges of our lifetimes. But, it can’t be addressed by energy austerity: meeting human aspiration for a better life is a must. Global society needs to build a new carbon-neutral sustainable energy infrastructure, but this will come with an enormous new demand for metals. However, traditional technologies for metal extraction from ores and their separation pose extreme environmental impact given the extraordinary demand needed.
Biomining (using microorganisms to dissolve minerals, separate, and concentrate metals) has the potential to provide selective and efficient access to metals from low-grade, globally distributed geologic and waste materials. Biomining is a growing reality: today it supplies 5 to 15% of the world’s gold and copper supplies from low grade ores. But, there are no industrially-useful microbes for either biomining most energy-critical metals. This means they will need to be built using synthetic biology with lessons from the natural world.
In this talk, I will describe work by my own lab to build genetically engineered microbes for biomining rare earth elements, for accelerated weathering and CO2 sequestration, and the new Microbe-Mineral Atlas Center.